省エネルギーとエネルギー問題
第1回 省エネルギーというテーマ
筆者が建築学科を卒業して電電公社の建築局に入ったのが昭和47年である。その翌年、第4次中東戦争が勃発した。これに伴い、石油危機騒動が起きた。そして「省エネルギー」という言葉が使われるようになった。空調設備設計を担当する当時の筆者にとって恰好のテーマとなった。
筆者の卒業論文は「高層建築の経常費調査」で夏休み期間に電力と重油の使用量を調べた。卒業論文の後に、卒業設計もあって気が重かった。開き直って、卒業設計テーマを「高層事務所ビルの空調設備」とした。単純な高層事務所ビルを設計し、電力費を低く抑える様々な策を講じた空調設備を平面図に描き入れ、システム系統図を加え、経常費を抑えるという設計意図を文章で書き加えた。
低温の冷水を作れない吸収式冷凍機から出た9℃の冷水の一部を顕熱負荷ばかりのペリメータゾーンのFCユニットに送り、残りを小型のターボ冷凍機に送って、更に5℃まで冷やしてインテリアゾーンに送るという奇想天外な方式を考えた。この他に、神田で買い込んだアメリカの雑誌に出ていたクーリングポンドを設けたり、回転型の全熱交換機を設置したり・・・同級生の卒業設計はケント紙20枚くらいだったり、立派な模型写真がついていたり。筆者のはケント紙6,7枚だけだった。模型も無く、図面の描き込みの密度も粗かったので合格できるか心配だったが、なんとめったにない優がつけられた。後に、井上宇一先生が前例の無い空調設備の卒業設計を高く評価してくださったと聞いた。前例の無いことをするのが、楽して高評価の秘訣という・・・
この当時、省エネルギーという言葉は未だ無かった。省エネルギーという言葉を初めて耳にしたとき、これは空調設計に都合のよい言葉だと思った。
大学卒業から33年の後、大学に転職してすぐに環境問題とエネルギー問題をテーマとしたパワーポイント教材を作った。その中からエネルギー系の2つの項目をピックアップし話題提供とする。更に、前回の故障・不具合研究の紹介に引き続いて、筆者のエネルギー研究を紹介する。
石油危機1973
石油は埋蔵量の限界と産油地の偏在から深刻な問題をひきおこしてきた。
筆者が学生の頃は、ノンポリであってもパレスチナ問題の歴史的背景くらいは知っていなければ同級生との会話も成立しなかった。大学に転職し、チャールトン・ヘストンの十戒も見たことない、パレスチナ解放なんて聞いたことも無い今時の学生のために色々な写真を使って、第4次中東戦争までの歴史を話した。
そもそも・・・・
BC2000年ごろ、創世記によれば、神はアブラハムにカナン(現在のパレスチナ)を与えると約束した。その後、孫のヤコブにも同じ約束を与えた。これが始まり・・・・
それから約600年後BC1400年ごろモーセはエジプトからイスラエル人を連れ出し、カナンの入り口まで導いたが、12人の斥候のうち10人の不信仰によって荒野を40年間さまようという不幸!
モーゼの後継ヨシュアによってカナンは征服され、約束の地に彼らは入った。その後BC1000年ごろにはサウル、ダビデ、ソロモンという優れた王たちによってカナンは乳と蜜の流れる約束の地になったかに見えた。しかし、その後の王たちがいけなかった。神に従わず、偶像を礼拝してしまった。
BC722年には北イスラエルがアッシリヤに、597年には南のユダ王朝がバビロンに滅ぼされ、王様はじめ役に立ちそうな人たちは捕囚として連れ去られた、というご存知バビロンの捕囚の不幸。その後、だんだん帰国する人が増えたが、ローマの支配下のそのまた支配下にあった。
そんなときにイエスが生まれた。しかし、イエスはほとんど関係ない。
ユダヤ人は何度も反乱を起こし、国家としての独立を達成することもあったが、その度にローマによって鎮圧された。なかでもバル・コクバ(星の子)の反乱(AD132〜135)の後には徹底的に弾圧され、パレスチナから追放という不幸。祖国を失ったユダヤ人は世界中に離散(ディアスポラ)する事になった。
ユダヤ人は、東と西に逃れて行った。東に行った人々の多くはハザール王国に住んだ。アシュケナジー・ユダヤと呼ばれるようになった。彼らはハザール王国の衰退と共にロシアに移動した。そこではロシア正教の大迫害に会うという不幸。
一方、西に逃れたユダヤ人はスペインに拠点を築いた。スペインの古名をスファラデイウムと言ったところからスファラデイー・ユダヤと呼ばれる。やがて、彼らもスペインを追放(1492年)され、ヨーロッパにちらばり嫌われるという不幸。ベニスの金貸し人肉抵当裁判のシャイロックもその一人、というのは勿論、冗談である。
20世紀になってテオドール・ヘルツルというユダヤ人の法律家がシオニズム運動を始めた。ナチスヒットラーに大虐殺される大不幸を経て、1948年(筆者が生まれた年だ)ついに2000年ぶりにユダヤ人の国家がパレスチナに出来たのである。
イスラエルが建国された1948年5月,さっそくアラブ諸国との第1次中東戦争が起こった。1956年には第2次中東戦争(スエズ戦争)、1967年には第3次中東戦争、そして、1973年10月、第4次中東戦争が起きた。17日間の戦闘後引きわけで停戦。実際上はイスラエルの敗北だった。アラブ諸国は,イスラエルを支持する国に石油を売らないという戦術をとり,世界を石油危機(オイルショック)におとし入れた。
ここでようやくオイルショック→省エネルギーに至るのだが、学生相手では、PLO,日本赤軍、テルアビブのロッド国際空港事件、重信房子、ミュンヘン・オリンピック事件、よど号ハイジャック事件も歴史的話題として加わる。
次に、石油メジャー、OPECについての基礎知識、湾岸戦争(1990年)、イラク戦争(2003年)について解説するのである。履修単位の無い筆者が興味を持ったことだけ写真を見せて自由に話す教養講座であった。学生たちは筆者のゼミに参加し、卒論指導を受ける義理を感じてということもあったろうが、ともかく聴講して、人間が辛抱強くなった。
次に、エンロン事件・・・実に興味深い事件であった。
第2回へ続く...
第2回 エンロン事件2001
エンロンは1985年に米国内の天然ガスパイプライン会社が合併してできた会社で、パイプラインの敷設運営をベースとして、天然ガスや石油を電力会社や工場などに売る事業をしていた。
90年代中ごろ、アメリカで電力自由化政策が始まると、エンロンは。パイプラインや貯蔵タンク、発電所といった施設を保有してエネルギーを供給する堅実な事業から、石油やガス、電力などの売買を仲介する「商社」としての欲望のビジネスに移行するようになった。
エネルギーは国際相場によって価格が変動する。電力会社やエネルギーを大量に消費する工場などではエネルギー価格の不確実性(リスク)を嫌う。エンロンはそこに着眼して欲望のエネルギー先物ビジネスを始めた。更に、この先物契約の権利を売買する欲望の市場を作り、自ら売り買いして利益を上げた。
株や債券の市場には、厳しい監視があり不正防止策がとられているが、エンロンが90年代後半に拡大させたエネルギー先物市場に対しては、欲望の政治献金のばらまきが有効に働き、不正防止強化策の立法が進まなかった。1997年からは利益を毎年急増させる決算を発表し、欲望の株価を急上昇させてきた。
2000年後半からの景気後退でアメリカのエネルギー需要が縮小し始め、エンロンのビジネス戦略は破綻に向かった。エンロンは、先物の契約が取れた段階で利益を計上していたが、実際には相場が予想と逆の方向に動いたときは損失が出てしまう。これを隠した。
2001年9月11日のテロの後、アメリカの景気は悪くなり、10月には粉飾によって損失を隠すことができなくなった。遂に、決算の修正を発表、破綻に至った。
エンロン破綻の原因は次の4点に集約される。
① デリバティブによる損失の先送り
10年を超える長期エネルギー取引のデリバティブ評価について、一般の短期市場取引同様の時価評価を採用していた。都合のよい価格を市場実勢と称して評価益を計上し高収益に見せかけた。
「積極型会計」(aggressive accounting)の手法をとる監査法人アーサー・アンダーセンはこのような操作を見逃してきた。
② 新しい金融手法による損失隠し
CFO(最高財務責任者)のファストウは、「ストラクチャード・ファイナンス」とか「アセット・ファイナンス」と呼ばれる新しい金融手法を活用して損失を隠した。
③ 海外事業の失敗
辣腕の美女レベッカ・マークが責任者となって、インドでの発電プロジェクトに30億ドルを投じるなど、世界37カ国で巨額のエネルギー・プラント事業を手掛けた。そのほとんどが失敗に終わっている。その損失をペーパー・カンパニーに移して隠し続けた。
④ワンマン経営と幹部の共謀
ブッシュ大統領(当時)の友人だった会長のケン・レイは高株価の維持のみを目標にした。社長のスキリング、CFOのファストウはじめ、幹部が不正を知りながら協力してきた。コーポレイト・ガバナンスが機能せず幹部全員が個人的な利益を追求した。
ミステリーもある。エンロン倒産の翌2002年、元副会長が拳銃自殺した。警察は自殺と断定したのだが、自殺としては不自然な点があり、様々な根拠から他殺と疑われている。
とにかく悪だくみ満載、呆れてものもいえない。
2002年に刊行されて直ぐに読んだ「虚栄の黒船 小説エンロン」(黒木亮)は面白かった。ドキュメンタリー映画もある。「エンロン 巨大企業はいかにして崩壊したのか?」(2006)はレンタルDVDで見た。
筆者の研究室に所属する3年生を主な対象として、できるだけ広い視野からの環境問題とエネルギー問題をテーマに写真と図だけで構成したパワーポイント教材を作ったのである。作っていて気付いたのだが、環境問題のパワーポイントにはレイチェル・カーソンはじめ女性が多数登場する。ところが、エネルギー問題の方は、ハニーブロンドの妖艶な(写真で見ただけだが)レベッカ・マーク(Rebecca MarkとEnronで画像検索)だけなのである。写真からの推量だが、たった一人でも、環境系の女性学者が束になってもかなわないフェロモンムンムン系存在感である。「分かち合う環境、奪い合うエネルギー」といったところであろうか。しかし、環境とエネルギーは切っても切れない関係、同時に論じられなければならないだろう。
以上、石油危機1973とエンロン事件2001は、パワーポイントで写真を映しながらの私の学生相手のおしゃべり(重ねて言うが授業ではない)の内容をあらためて文章にしたのだが、WEBから多くを引用したり参照したりしている。
第3回へ続く...
第3回 筆者のエネルギー研究紹介
建築における省エネルギーは、これを推進するために、温暖化抑止効果など社会的意義、及び経済性とともに検討されるべきである。このような観点から、筆者は、ESCO事業におけるインセンティブの研究1)、炭素税の効果推定の研究2)、CO2排出権価格との関係性の研究3)などを行ってきた。
エネルギー消費量は建物設計時の推定ばかりが重要なわけではなく、各保全現場での消費量管理がなされねばならない。また、水の消費量管理も同じように行われるべきである。この仕事の基本は消費量実績値の評価である。このような観点から、筆者は、上水使用量等に関する研究4)、全電力ビルにおける電気使用量に関する研究5)、DHCから熱供給を受けているビルにおける熱使用量に関する研究(小松と共同)6)を行ってきた。
論文5は、中規模全電力インテリジェントビルにおける電気使用量の変動要因を挙げ、これらに対応する説明変数を検討し、電気使用量を目的変数として実績データから重回帰により、それぞれの変動要因の影響の程度を分析するとともに、既存建物において過去の実績から簡易に管理基準値(当該建物の諸事情、諸特性に対して標準的な電気使用量)を求める方法を提案している。
同様の分析方法により、永峯らと共同の東洋大学キャンパスを対象とした研究7)、当時大学院生だった吉野との病院のエネルギー消費量を対象とした研究8)がある。
実は、大学在職中に学生と行ったエネルギー消費量データの分析で、論文にまとめていない中途半端で止まっているテーマが残っている。これも何とかしなければならない。
文献リスト
- 高草木明:既存建物の省エネルギー化促進のための経済性の成果に対するインセンティブに関する研究,日本建築学会計画系論文集, NO.508,pp.193-200,1998年6月
- 高草木明:建築設備の省エネルギーと炭素税との関係性に関する研究,日本建築学会計画系論文集,NO.526,pp.43-50,1999年12月
- 高草木明:建築設備の省エネルギー策の経済性とCO2排出権価格との関係性に関する研究、日本建築学会環境系論文集, NO.604,pp.101-107,2006年6月
- 高草木明:事務所建物における上水使用量、一般廃棄物量と衛生設備の故障・トラブル発生件数の実態調査研究,日本建築学会計画系論文集, NO.551pp.69-76,2002年1月
- 高草木明:中小規模事務所建物の電気使用量の実態とその変動要因に関する調査研究,日本建築学会計画系論文集,NO.554,pp.101-108,2002年4月
- 小松正佳,高草木明:中規模賃貸事務所ビルにおける熱使用量の実態調査研究,日本建築学会環境系論文集,NO.593,pp.57-64,2005年7月
- 永峯章,高草木明,成實悠樹,吉野大輔:東洋大学の4箇所のキャンパスにおけるエネルギー消費量に関する調査研究,日本建築学会環境系論文集, NO.653,pp.661-668,2010年7月
- 高草木明,吉野大輔:大規模病院におけるエネルギーと水の消費量に関する調査研究,日本建築学会技術報告集,No.35,pp.233-238,2011年2月
(2015年5月28日 高草木明)
「富士山」の噴火に対する備えを
第1回 「日本列島の火山も活動期に」
我が国には、全国110の活火山がある。世界的に見ても有数の火山国である。火山は美しい景観や温泉など観光地として人々を楽しませてくれる。しかし、いったん噴火すると大きなエネルギーを放出し、火山近傍では噴石、火砕流、火山ガス、溶岩流、土石流、山体崩壊(岩屑なだれ)のほか、広域にわたる火山灰の降灰により、人々の暮らしに甚大な被害を及ぼす。
日本のシンボルとして親しまれている霊峰「富士山」(標高3776m)。 美しい表情をもつ「世界文化遺産」にも登録された、この独立峰は、雄大な裾野をもつ成層火山として、高さ、山体の大きさで、我が国最大の活火山であることは誰もが知っている。最近、この富士山が眠りから覚めて大噴火を起こすのではないかと話題に上ることも多くなってきた。先般、木曽の御嶽山が犠牲者の出る噴火を起こして、世の中の関心が高まったこともあるが、ここでは関連する動き動向についてやや科学的に紐解いてみたい。
これまで世界各地で発生したマグニチュードM9規模の巨大地震では、その影響で近傍の活火山が全て4年以内に大噴火しているという前例がある。東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日、M9.0)からもうすぐ4年になるが、日本列島の火山も活動期に入ったとされる。我が国では火山の大規模な噴火はこの千年で20数回発生している。最近では1914年桜島大正噴火、1990年雲仙普賢岳噴火などがあげられ、頻度的にみてもいつ起きてもおかしくない。
2014年9月27日11時52分、長野県と岐阜県の県境にそびえる「御嶽山」(3067m)が、突然、噴火した。行楽シーズンの休日であり、噴火で不意を打たれた登山中の数百人が巻き込まれ、雲仙普賢岳の43名を超える戦後最悪63名の死者・行方不明者が出てしまった。今回の噴火は地中のマグマそのものの噴出ではなく、マグマによって熱せられた地下水が地上に噴出する水蒸気爆発であった。噴火の前兆とされる火山性地震が1か月ほど前から観測されていたが、マグマ活動を示す火山性微動や地殻変動がなく噴火を予測できなかったとされる。水蒸気爆発のような規模の小さな噴火は予知が困難といわれる。
御嶽山は日本百名山の一つであり、3000m級の山としては比較的登りやすく人気があった。しかしながら、活火山のなかでも気象庁により常時監視されている噴火の危険性の高い47火山のうちの一つでもあった。気象庁では、このうち危険度の高い30火山に対して5段階の噴火警戒レベルを発表している。御嶽山の当時の噴火警戒レベルは1(平常)であったが、噴火直後、警戒レベル3(入山規制)に引き上げられている。有識者の集まりである火山噴火予知連絡会(気象庁)は予測できなかったとの見解であるが、火山性地震の頻発を受けて、もっと早い時点で入山規制すべきだったのではないかとの指摘も各方面から聞こえ、悔やまれる。
御嶽山は長らく死火山とも言われていた山であったが、1979年に有史以来、突如として噴火した。以後、死火山、休火山という用語は使われなくなった。そのきっかけとなる噴火であった。その後も1991年、2007年に小噴火しているが、そのときはいずれも死者等は出なかった。そして今回2014年の大参事に至った。いずれにしても、いまの科学では火山の噴火時期や規模の予知は難しいということが、図らずも露呈してしまった。
御嶽山は、火山としては富士山に次いで2番目に標高の高い中部日本の3000m級の独立峰であり、富士山の兄弟分のような大きな裾野をもつ成層火山である。その御嶽山が死火山と思わせるような長い沈黙を破って活動期に入ったということも、富士山の噴火を危惧させる要因の一つになっている。このほか東日本では、火山性地震が頻発している草津白根山、上高地焼岳や、群発地震が起きている那須岳、日光白根山、このほか浅間山、吾妻山、十勝岳などは、いずれも噴火する恐れがあり、要注意とされる。
第2回「富士山は噴火を繰り返して急成長した若い火山」
一方、小笠原諸島の西側に、富士山級の巨大な海底火山の頂上付近が、わずかに海面上に顔を覗かせている無人島「西之島」がある。この付近の海底が2013年11月に大噴火を起こし、流出した大量の溶岩により島ができ、西之島と繋がって島全体の面積がもとの10倍、東京ドーム50個分を超える勢いで、いまでも拡大している。これは「日本海溝」の南側の続き、「伊豆・小笠原海溝」近傍での出来事であるが、東北地方太平洋沖地震も影響しているのではないかとも言われている。
その理由は、東北地方太平洋沖地震の震源は日本海溝、すなわち「太平洋プレート」が日本列島の載る「ユーラシア(北米)プレート」に衝突し、その下に潜り込む場所であるが、同じ太平洋プレートがその南どなりで「フィリピン海プレート」の下に潜り込む場所が伊豆・小笠原海溝だからである。我が国の火山のもととなるマグマは、こうして潜り込んだプレートに含まれる水分が分離して軽いので上昇し、重なる上のプレートに入り込んで岩盤の一部を溶かして作られる。水は岩石の融点を下げる働きがある。また巨大地震はプレート同士の衝突とその反動によって発生し、周辺岩盤の応力状態を変化させてマグマの上昇をうながす。それで日本列島は火山と地震が多く、しかも連動しているとされる。
伊豆・小笠原海溝と言えば、伊豆諸島の三宅島で大量の火山ガスにより3800人の全島避難を余儀なくされた「三宅島噴火」(2000年)が思い出される。三宅島や伊豆大島も大噴火の危険性があるといわれる。西之島の噴火で、この伊豆・小笠原海溝を震源とする巨大地震の可能性も高まっていると指摘する専門家もいる。いま次なる大震災を引き起こすのではないかと危惧されているのは「南海トラフ」を震源とする巨大地震とそれに伴う巨大津波であるが、伊豆・小笠原海溝で巨大地震が発生しても、我が国の太平洋岸には巨大な津波の襲来が想定される。ちなみに、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に潜り込むところが南海トラフである。また水深が6千mより浅い海溝をトラフという。
そして「富士山」は、これら太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートの3枚のプレートがぶつかり合い重なっている頂点、世界的にも珍しい場所に位置する。富士山はここ10万年で大噴火を繰り返して急成長した若い火山であり、近年1300年間に10回も噴火を繰り返している。1707年の宝永噴火を最後に300年も鳴りを潜めているが、そうした時期の方が珍しく、そろそろ目覚めてもおかしくない。東日本大震災後、まさに噴火を始めた富士山級の大型火山である御嶽山と西之島の間に位置することも不気味といえる。
富士山は2200年前までは山頂噴火を繰り返してきたが、その後は山頂以外の中腹から噴火している。噴火のデパートと呼ばれるほど、大小さまざまなタイプの噴火を引き起こしてきた。東日本大震災は平安時代869年に東北地方を襲った「貞観地震」(M8.3以上)の再来ともいわれるが、富士山はその5年前に大噴火を起こしている。この「貞観大噴火」(864年)では、富士山の北西山麓から2年間にわたって大量の溶岩を噴出し、溶岩流が固まった上に形成されたのが、現在の「青木が原」樹海である。これによって、当時「せのうみ」と呼ばれていた湖が分断され、「富士五湖」ができた。
また江戸時代に起こった「宝永大噴火」(1707年)では、南東斜面で爆発的な噴火を起こし、短期間に大量の火山灰を噴出した。その痕跡はいまも宝永火口として残っている。噴火は宝永4年(1707年)12月16日から16日間続き、江戸を含む広範囲に火山礫や軽石、火山灰が降り積もった。田畑は全滅し、雨が降るたびに土石流が洪水を引き起こし、噴火後数十年にわたって人々の生活を苦しめた。
第3回「富士山噴火の想定」
宝永噴火は、今でいう南海トラフ巨大地震である「宝永地震」(M8.6程度)の発生49日後に始まっていて、巨大地震と火山噴火の関係はここでも認められる。富士山は現在、顕著な噴火の兆候はないが、太平洋プレート、フィリピン海プレートが引き起こす巨大地震と明らかに連動しており、山体膨張の兆しも報告されてマグマをため込んでいると思われ、最大限の注視が必要となっている。宝永噴火は桜島大正噴火より小さく、雲仙普賢岳噴火の数倍の規模とされるが、首都圏に隣接しており、こうした大規模噴火が起こったとき、どのような事象と被害が発生するか、次に示すように様々な想定がなされている。
火口近傍は、噴石(火山礫、軽石等)が降り注ぐほか有毒な火山ガスや、時速100kmを超える火砕流、融雪型火山泥流、降雨による土石流が発生し、避難が間に合わない可能性がある。また溶岩の流出が発生した場合は、温度1000℃に達する溶岩が、人が歩く程度の速さで流れ下る。青木が原を形成した貞観噴火規模の溶岩流が富士山の南側で発生すれば、日本の大動脈である東名高速道路、東海道新幹線まで到達する可能性があり、日本は東西に分断されて社会活動、経済活動に重要な支障が生じる。
さらに最悪の想定は、山の一部が崩れる山体崩壊が起こるケースであり、富士山でも約2900年前に発生している。いまの三島市街周辺まで岩屑なだれが高速で流下した痕跡があり、これと同じ規模の山体崩壊が起これば、避難が間に合わず10万人単位の被害が出る恐れがあると言われている。西側が崩れれば駿河湾にまで流れ込む可能性もある。
噴火に伴う火山灰は、広域にわたり深刻な被害をもたらす。宝永噴火では、約7億m3(東京ドーム5百杯分以上)の火山灰が、偏西風に乗って当時の江戸周辺、関東一円に大量に降り注いだ。いま同規模の噴火が起こった場合、東京、横浜、千葉一帯には、空気中の水分を吸って黒い雨のようになった火山灰が数時間で到達して、あたりは昼間でも薄暗くなり、東京都心では噴火4時間後には1cm程度、2週間で10cm以上降り積もるとされる。小田原では50cmにも達する。
火山灰の成分は、マグマが噴火で破砕・急冷したガラス片・鉱物結晶片であり、火山ガス成分が付着して弱酸性、水分を吸った灰は電気を通し、乾くと固結する。普通の焼却灰ではなく、吸い込んではならず、口や鼻に入れば粘膜や肺が傷つき、目に入れば角膜が傷つく。外出は控えた方が良く、外出には防塵マスクや防護メガネの準備が必要であり、コンタクトレンズは使えない。
降灰が社会インフラに与える影響は大きく、まず首都圏の交通機能は完全に麻痺してしまう。車は道路に火山灰が数mm積もるだけでスリップしフィルタも詰まるので走れなくなってしまう。鉄道は線路上の灰が濡れると運行制御システムが誤作動を起こし運行は困難になる。また航空機はエンジンが火山灰を吸い込むと故障するので飛べなくなる。
一方で、首都圏は大停電に見舞われる可能性がある。湿った火山灰が送電線に付着し短絡して停電を引き起こすのと、さらに東京湾岸の火力発電所ではフィルタの目詰まりで発電用タービンを回せなくなる可能性がある。太陽光発電もできなくなる。また水源地に大量の火山灰が降ると、取水口の目詰まりで上水道が利用できなくなる。下水道も大量の火山灰の流れ込みにより機能不全になる恐れがある。
第4回「前兆現象を捉えてから噴火するまでの時間的余裕はない」
長時間にわたる大停電は、経済活動や医療活動などに深刻な影響を与える。地震の際と異なるのは、停電に備えて用意した非常用発電機が、灰の吸入を防ぐフィルタ機能に限界があり、使えなくなる可能性がある。同じように空調設備や冷却が必要なコンピュータ、サーバーの類もストップせざるを得なくなる。電子機器は灰を内部に取り込むと故障してしまう。携帯電話も中継設備に火山灰が付着して使えなくなる可能性がある。都市ガスの供給も止まると考えておいた方がよい。
富士山に最も近い原子力発電所は浜岡原発であるが、その距離は90km、溶岩がここまで迫ることはまず考えられないが、風向きによっては火山灰が降る可能性があり、核燃料の冷却機能を確保するための対策が必要とされる。
農業被害は火山灰が農作物や草木を覆いつくすと、収穫不能や収量・品質低下、さらには土壌の酸性化など深刻なものとなる。水分を吸った灰は雪より重く30cm積もると家屋倒壊の可能性があるとされる。なお噴火による建物被害は地震保険により補償の対象になる。膨大な量の火山灰は捨土扱いで処分場を作って集積することになるが、その処理は大きな課題になることが予想される。
富士山では現在、GPS、地震計、傾斜計、空振計、監視カメラなどにより、火山性地震や地殻変動など噴火の前兆を24時間監視している。データに異常があればすぐ対応できる体制が整備されており、大規模噴火であれば数週間前には兆候が現れるとされる。しかし、確実な前兆現象を捉えてから噴火するまでの時間的余裕はあまりないと考えるべきと専門家は言っている。しかも火口の位置は、可能性のある範囲が広すぎて噴火直前まで確定が困難とのことである。
全国の主要な火山については、自治体から火山被害の危険が及ぶ区域を示した噴火ハザードマップが公表されている。富士山の噴火についても、2004年に富士山噴火ハザードマップが作られ、周辺市町村の各戸に配布されている。2006年2月には政府(中央防災会議)から「富士山火山広域防災対策基本方針」が出されたが、観光地でもあり防災はタブー視される風潮さえあった。防災意識が高まったのは東日本大震災後であり、世界文化遺産登録の動きもあって、2012年6月に静岡・山梨・神奈川の3県による「富士山火山防災対策協議会」が発足し、2014年2月には火砕流、噴石、溶岩流、融雪火山泥流等に対する広域避難基本計画が発表された。なお山体崩壊等を伴う巨大噴火は、頻度が著しく低く、今後の検討課題で対象外としている。
火山の近傍では噴火に対して迅速な避難が必須となる。避難計画では、あらかじめ想定した火口からの距離等で定めた1〜4次避難対象エリア内の対象者について、噴火前と直後、噴火開始後に時間を追って段階的に避難する計画になっている。対象者は一般市民、避難行動要支援者、観光客(登山者)に分け、観光客は入山規制で対応するとしている。火口形成、火砕流、大きな噴石、火山泥流への対応については、時間的に余裕がないため噴火前から想定火口周辺の全方位で避難対象エリア外に避難する。一方、流下速度の遅い溶岩流については噴火後、流下状況に応じて流下ラインのみで避難することになっている。
避難対象者数は溶岩流によるものが多く、溶岩が西側に流下すれば富士市、富士宮市など最大約24万人、東側に流下すれば御殿場市など最大約17万人、北側では富士吉田市など最大約9万人と想定されている。これにもとづき、ハザードマップの改定や避難訓練が実施されている。富士スバルラインなどの道路が使えなくなることも想定して、現在使われていない登山道を利用した避難も検討されている。
第5回 最終回
火山から離れた地域では、降灰対策と降灰後土石流への対応が必要となる。東京都では「地域防災計画」(火山編)の中で、富士山噴火に伴う降灰対策、噴火警戒レベルに応じた体制整備などが明記されている。しかし、まもなく富士山が噴火するという警報等が出れば、パニックになって水や食料、防塵メガネ・マスク、清掃用具、フィルタなど必需品の買占めが起こり、品不足になることは目に見えている。時間帯によっては、東京都心など大量の帰宅困難者が発生することも想定される。
富士山の降灰が予想される地域に、首都機能の集中している東京がある我が国は、思った以上に噴火に弱いということを再認識する必要がある。電車も動かない、車も使えない、大停電が起こる、水も出ない、コンピュータも使えない、携帯電話も繋がらない、外出すると目が痛い、呼吸も苦しい、社会活動や経済活動が大混乱に陥る可能性が高い。物流も途絶え、長期化する可能性もあり、地震や津波とはまた異なる備えが必要である。企業の事業継続を考える上でも要注意の災害といえる。
世界文化遺産でもある富士山が噴火して、山容が変わったとき遺産登録はどうなるのか気になるところでもあり、美しい景観が損なわれることのないよう願うのは全国民の思いでもあるが、大自然の営みは人知を超えており、タブー視せず荒々しい側面をもつことも頭に入れておく必要がある。目を背けることなく、普段から最悪の事態を考えて、噴火に対する準備を怠らないことが肝要と思われる。
(2015年2月16日 赤木久眞)
※掲載された論文・コラムなどの著作権は株式会社NTTファシリティーズ総合研究所にあります。これらの情報を無断で複写・転載することを禁止いたします。 また、論文・コラムなどの内容を根拠として、自社事業や研究・実験等へ適用・展開を行った場合の結果・影響に対しては、いかなる責任を負うものでもありません。
ご利用になりたい場合は、当社ホームページの「お問合わせ」ページよりご連絡・ご相談ください。
NTTファシリティーズ総合研究所 EHS&S研究センター
Copyright c 2015 NTT Facilities Research Institute Inc.
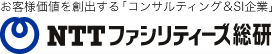
 基調講演 中井 検裕先生
基調講演 中井 検裕先生



 会場の様子
会場の様子